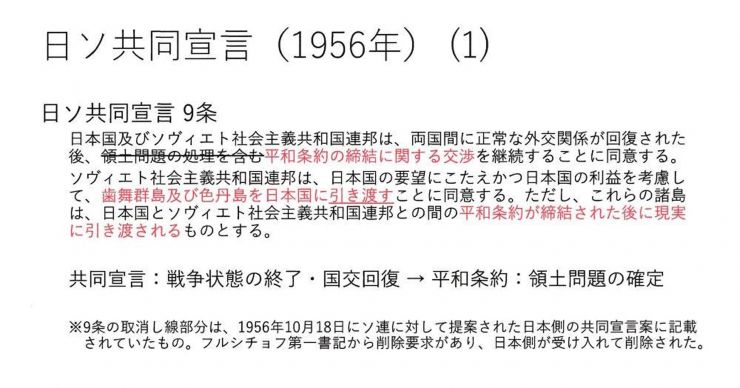シベリア出兵とイワノフカ事件(日本ユーラシア協会愛知県連合会)
1、シベリア出兵と イワノフカ事件
1、 イワノフカ事件とは
イワノフカ村はロシア共和国アムール スカヤ州の 州都、ブラゴベシェンスク市から車で1時間の農業の村(セロー)です。
この村をソヴィエト連邦が崩壊してから間もない1991年に全国抑留者補償協議会会長の斎藤六郎氏が訪れました。その目的は、ロシアの地にまだ放置されていたシベリア抑留者の遺骨の調査です。
斎藤氏は当時の村長だったウス氏に会い、訪問の目的を話しました。ウス氏は言葉を返しました。
「あなた方日本人はこの村がどんな村か知っているか」
ウス氏は斎藤氏を村にある2基の記念碑に案内しました。碑には次のようなロシア語が刻まれていました。
「1919年3月22日 日本の干渉者たちによって257名のイワノフカの住民が射殺された」
「1919年3月22日 この地において日本人達は36名のイワノフカの住民を焼き殺した」
事の重大さを理解した斎藤氏は、その後何度かイワノフカ村に足を運び、ウス村長と話し合いを重ねました。その結果、次のことで合意しました。
一、 日本はシベリア出兵の時にイワノフカ村に放火し、約 300人の村民を殺したことを懺悔する。
二、 ロシアは1945年に日本人を不当に抑留し、約6万人の日本人をロシアの地に死没させたことを懺悔する。
そして1995年7月にこれらの合意を象徴する「日露共同の追悼碑」がイワノフカ村の中央に建立されました。
「日露共同追悼の碑」が完成した1995年12月、齋藤六郎氏は急逝されました。
斎藤氏の事業を引き継いだのが横山周導氏です。横山氏は1944年、20歳で満州の日本軍に召集されました。翌1945年8月9日、ソ連軍が満州に進撃を開始しました。横山氏が配属された部隊も戦闘態勢に入りましたが、8月24日には戦闘停止命令が出て、ソ連軍の捕虜とな ることを余儀なくされました。
横山氏はソ連領のコムソモリスクまで連行さ れ、道路、鉄道の建設、森林伐採などの重労働に動員されました。支給された食料はパンとスープだけ。多くの戦友が死んでいく中で、やせ細りながらも生き延び、1947年の8月に日本に帰国すること ができました。
故郷の岐阜県で教員生活に入った横山氏でしたが、異国の地で亡くなった戦友達に対する哀悼の思いは強くなるばかりでした。せめて墓参だけでもと思っても、平和条約を結んでいないソ連への渡航は困難で した。
ようやく1983年 に斎藤氏とともにソ連に入国することができました。この時、横山氏が見たもの は、荒れ放題のお墓と放置されたままの遺骨でした。
2007年、横山氏はNPO法人「ロシアとの友好・親善をすすめる会」を組織し、遺骨収集と墓参の旅を始めました。
この横山氏の行動に、ロシアの住民の中から共鳴する人々が現れました。ハバロフスクやアムールスカヤ州の国際交流団体の人達は、横山氏に日本人墓地の情報を提供し、道案内までしてくれました。自分の所有する農場や工場の敷地を日本人墓地用に提供した人達もいました。
「すすめる会」とロシア住民との交流はさらに深まり、2018年にはイワノフカ村の少年少女13人 が岐阜県揖斐川町を訪れ、「日露交換コンサート」を開催し、華麗な歌舞を披露してくれました。
同じ2018年の8月 には、イワノフカ村事件100年を偲んで「すすめる会」は36人の墓参団を編成してイワノフカ村を訪れました。 日露合同慰霊碑の前で、日本人僧侶6人とロシア人の正教の 司祭が犠牲者を供養しました。
墓参の旅について
第1期 1983年~1995年 11回
第2期 1996年 ~2006年 10回
第3期 2007年~2019年 12回

イワノフカ事件 36人焼き殺しの絵

イワノフカ事件の絵を見る横山周導氏

イワノフカ村の入り口にて

星の慰霊碑の前にて

炎の慰霊碑

炎の慰霊碑の下の銘板に書かれている言葉

日ロ共同慰霊碑の前で

イワノフカ村で唯一焼け残った教会(ペンキが塗られて今はきれいになっている)

イワノフカ村の子供たち
3、シベリア出兵とは
シベリア出兵とは第一次世界大戦中の1917年11月、ロシアで世界最初の社 会主義革命がおこり、ロシアはドイツと単独講和を結んだ。ここで慌てた英仏など欧州の連合国はドイツが西部戦線に兵力を集中するのではないかと予想して、パリで最高軍 事会議を招集した。この会議で懸念されたのが、ロシア極東の港町・ウラジオストクに積み上げられていた63万 5千トンの貨物だった。この貨物は軍需品や鉄道敷設の材料などでこれらをドイツ軍の手に落ちる前に処理すべきだとの結論で一致した。
そこでイギリスとフランスは日本とア メリカに派 兵を要請する。イギリスは日本が単独出兵すれば東部シベリアを植民地にしかねないと警戒してアメリカとの共同出兵方式を選んだ。
しかしアメリカはこの武力干渉に自国 はもとより 日本の出兵にも反対すると表明した。だが日本の軍部はアメリカの反対を押し切ってでも出兵すべきだと強硬だった。参謀次長・田中義一は意見書を出して、シベリア出兵の持論を展開する。当時日本は韓国を併合し(1910年)、日露戦争で得た南樺太と中国遼東半島の租借地、それに台湾を植民地とし、それらは日本の国土面積の77%にも達していた。
軍部はともかく政府内にはシベリア出 兵の慎重論が大勢を占めていた。航空機や機銃などの準備を始め糧食の用意すらできていないというのがその主たる理由だった。また日本経済は対米依存であり、アメリカの協力を得られない出兵は認められないという意見もあった。
海軍は「居留民保護」を目的に1918年1月、戦艦「石見」、「朝日」が強行入港する。陸軍参謀本部は「居留民のため極東露領に対する派兵計画」を策定しており、参謀次長の田中義一はバイカル湖以東に反革命政権の独立自治国家を形成させ たいと考えていた。
シベリア出兵を求める形勢が一転したのは1918年7月8日だった。アメリカが共同派兵を提議してきたからである。ロシア国内に取り残された「チェコスロバキア軍団」の救援が目的だった。だがアメリカの条件は、あくまで「限定出兵」であった。アメリカは日本に共同出兵を提議するも、兵力は両国とも同数の7,000とし、派兵地域も限定していた。しかし日本は派兵を12,000とするよう合意させた。シベリア出兵は宣戦布告がないものの、事実上のシベリア戦争だった。シベリア出兵宣言から3か月後の派兵数は、ウラジオストクからの上陸部隊と満州里から国境を越えた部隊を合わせて、戦闘員は4万4700、非戦闘員は2万7700の計7万2400にのぼる。
極東ロシアに「拡大派兵」した日本軍 は、シベリア東部に親日の自治政府(傀儡政権)を樹立すべく、反革命派のセミョーノフ軍などを支援してきた。だが主導権争いから、黒海艦隊の元司令官コルチャークが 将校たちに担がれて「全ロシア臨時政府の最高執政官に就いた。シベリア鉄道の主要駅オムスクを拠点としたので「オムスク政権」と呼ばれる。
陸軍第五師団(広島)がシベリアのザバイカル州 に入ったのは、1919年の夏だった。イワノフカ村の焼き打ち事件を惹起した「田中大隊の全滅」か ら半年後のことである。陸軍の第七師団(旭川)が東シベリアのザバイカル州に入ったのは1918年9月上旬だった。第七師団は日露戦争で、ロシアから譲渡された中国東北部の(満州守備)にあたっていた。第七師団は、ボリシェビキ軍と交戦を続けるチェコ軍やセミョーノフ軍を支援して、満州各地からシベリア東部の主要地域までを占領している。これに対して労働者 や農民による非正規軍の武装集団パルチザンは、日本軍の駐留に反対してゲリラ戦を挑んだ。
極東ロシアに「拡大派兵」した日本軍は、シベリア東部に親日の自治政府(傀儡政権)を樹立すべく、反革命派のセミョーノフ軍などを支援してきた。だが主導権争いから、黒海艦隊の元司令官コルチャークが 将校たちに担がれて「全ロシア臨時政府の最高執政官に就いた。シベリア鉄道の主要駅オムスクを拠点としたので「オムスク政権」と呼ばれる。
陸軍第五師団(広島)がシベリアのザバイカル州に入ったのは、1919年の夏だった。イワノフカ村の焼き打ち事件を惹起した「田中大隊の全滅」から半年後のことである。陸軍の第七師団(旭川)が東シベリアのザバイカル州に入ったのは1918年9月上旬だった。第七師団は日露戦争で、ロシアから譲渡された中国東北部の(満州守備)にあたっていた。第七 師団は、ボリシェビキ軍と交戦を続けるチェコ軍やセミョーノフ軍を支援して、満州各地からシベリア東部の主要地域までを占領している。これに対して労働者 や農民による非正規軍の武装集団パルチザンは、日本軍の駐留に反対してゲリラ戦を挑んだ。
ウラジオ派遣軍の陸軍第一二師団歩兵第一四連隊に所属した松尾 勝造上等兵の体験
「シベリア出征日記」より
家の中より物陰より盛んに発砲して 来るが、その時はもう身の危険などとの考えは微塵も起こらない。一昨日の恨み、戦死者の弔い合戦だと身の疲労を等とうに忘れてしまい、脱兎の如くに攻め入った。その 勇敢さは、敵方より見た時は如何に恐ろしく見えたことであろう。硝子を打ち割り、扉を破り、家に侵入、敵か土民かの見境はつかぬ。手あたり次第撃ち殺す、突き刺すの阿修羅となった。前もって女子供、土民を殺すなと注意されてはいたものの、敵にして正規兵はごく少数、多くは土民に武器を持たしたもの、武器を すてれば土民に早変わりという有様にて、兵か土民かの見分けは付こうはずがない。片っ端から殺していく。敵の兵力は一千と聞いた。逃げたとしてもまだ何処 かに潜んでいようと、一軒毎家探しをしたところ、作物を貯蔵している地下室に兵か、土民か、折り重なり息を殺して隠れている。奥の方は暗くて何人いるかわ からない。一発ボーンと放っておいて、「イヂシュダー」(こっちへこい)と怒鳴ると、銃や剣はすててまづ両手をあげて、次に手を合わせ拝みながら上がってくる奴を戸外に連れ出し、撃つ、突く等して死骸の山。かかる時、正規軍は橇や馬に乗って一番に逃げ、あとは土民兵に抗戦させるのが習い。


鉄道労働者を殺した日本介入軍

(左)アムール鉄道の日本軍装甲車 (右)山田乙三少佐

ウラジオストクに進駐する日本軍
「シベリアに逝きし46300名を刻む
村山常雄著 七つ森書館
2009年8月15日発 行 2000円+税
「シベリア抑留者60万、それらの人たちの体験はおなじようであり、また60万例、まったく別個の体験だったであろう。そのうち、故郷や家族を思いながら、ついに日本の土を踏めなかった無念の死者は、6万前後といわれている。そのひとりひとりの死にこだわりつづけたのが、この「シベリアに逝きし46300名を刻む」である。
4万6300人。
これは70歳からパソコンをはじめ、何度もロシアの地を訪ね、10年がかりで入手した、死亡者名簿を反訳、整理した村山さんのデーターベースに記録された人名である。村山さんは、それを「死亡者総数の最低値」という。これ以外の死者は、いまだ名乗りを上げることができない。名簿の空白は、シベリアの土中の暗闇そのものである。
名前の確定は人間性の回復だった。この膨大な 仕事は、国家に関係なく、自己犠牲的な個人の営為だった。その村山さんがこう主張している。
「シベリアの凍土に“埋葬”という名で放置さ れ、いまだ氏名さえも明かされぬ無言の兵士たち幾万。『シベリア抑留』は、その全解明になお遠く、その事後処理も不十分であり未完である事実に、国とその構成員たるわれら自身がいまこそ立ちどまり正対しなければならぬ」
はしがき
死者は一人ひとりねんごろに、その固有の名を読んで弔われるべきであり、この人たちを「名もなき兵士」や「無名戦士」と虚飾して、人類史の襞に埋め戻す非礼は決して許されることではありません。名を呼び、問いかけ、その声を聴く。そんな真心をこめた祈りこそが、真の「弔問」であり「慰霊」となり、弔問者自身とそれを含む国と社会の再生を促す力ともなる のではないでしょうか。
すべて戦争犠牲者名簿は、第一義的にかけがえない人間一人ひとりの無念と命の尊さを、重くその固有の氏名に刻んで歴史に残すものでなければならない。
第2章 シベリア抑留とその違法性
1945年(昭和20年)8月、第2次大戦終結時、連合国間の取り決めによりソ 連軍占領地域とされた満州(中国東北部)、関東州(遼東半島)、北朝鮮、南樺太および千島列島において、敗戦を迎え武装解除された日本軍将兵(一部民間人を含む)60万余が、ソ連の独裁的権力者スターリンの指令により、軍事捕虜としてソ連領(一部はモンゴルなど)に抑留され労働を強制された結果、6万余の尊い犠牲者を輩出する悲劇を生んだ。
一般にこの事実は、象徴的な意味において”シベリア抑留”と呼ばれている。しかし、その地理的範囲はたん にシベリアのみでなく、極東ロシアをはじめとする広大なソ連領のほとんど全域に及び、そこにわが国史上最大多数の同胞が集団的に拉致され、しかも戦争終結 後の平時において、長期間(大部分は4年以内、最長11年 間)にわたり抑留され、多数の死をもたらした歴史的事件であるが、この悲劇の発端は、まずソ連による国際条約無視の不法な対日参戦にあったことを強調しな ければならない。
すなわち、1941(昭和19)年4月に締結され、5年と定められた「日ソ中立条約」の 有効期間中に、ソ連はこれを一方的に破棄し、突如として満州(中国東北部)・朝鮮・千島・樺太等に駐屯する日本軍攻撃の挙に出たのである。
近代国家においてはたとえ交戦中であっても、ましてや停戦後、さらに終戦後はもちろん、捕虜とされたものに対してはその生命と人権を保障し、自国の軍隊並みの給与を行い、一定の労働を求めるほか精神 的・肉体的苦痛を課してはならないとするのが、国際法の規定であり近代国家間の常識である。
しかしスターリンのソ連は全くこれを無視した。すなわち満州(中国東北部)等の占領地域において捕獲した日本人を、自国領土の受け入れ条件未整備の地に強制移送し、酷寒と劣悪な衣食住環境の中に投 入して、しかも労働を強制した。それは捕虜に対する前近代的な奴隷的処遇というべく、そこに酷寒・飢餓・重労働の極限状況、世にいう”シベリア三重苦”の世界を現出させた。
抑留当初8か 月間の死者発生状況
|
1945年9月 |
135名 |
1946年1月 |
6,876名 |
|
10月 |
803名 |
2月 |
5,508名 |
|
11月 |
2,275名 |
3月 |
3,929名 |
|
12月 |
4,519名 |
4月 |
2,335名 |
1991年4月、「捕虜収容所に収容されていた者に関する日本国政府とソ連邦政府との間の協定」が締結され、ゴルバチョフ大統領は持参した3万8000人の「ソ連抑留死亡者名簿を日本政府に提 出した。
1993年10月11日、ロシア大統領エリツィン訪日
「日本からの墓参に全面的に協力するし、遺骨の 発掘とか日本への輸送という面についても全力を尽くしたい。ロシア国民を代表して、この非人間的な行為に対して謝罪の意を表明する」
しかしエリツィン大統領の謝罪は、具体的な問題解決策に踏み込まなかった。加害の事実を認め心底謝罪するということは、同時に誠実な「償い」への決意表明でなければならない。しかるにエリツィン氏には それがなかった。
第3章 シベリア抑留における大量死の実態
現在の常識からは想像困難であろうが、抑留開始 後数か月間の兵士たちの体力と健康度は、一部の例外を除けば、特に下級兵士において一様に数十歳分加齢したほどに落ちていたと私は考えている。
最下級である二等兵の私が最初の分所に入所し たのは19歳、1945(昭和20)年10月だったが、ひと月後の11月の身体検査で、後姿で軍医の指につままれた私の尻の皮は4~5センチも伸びて、すでに老人同然の退化を示したし、またこの時期、私も同僚も歩行途中によく転んだ。1センチ程度の小石や親指ほどの小枝につまずいて、そのたびに転ぶのである。やせさらばえた枯れ木のごとき肉体と、その痩体を支える筋肉がすでに底をついていたのだ。
関東軍は、敗戦(1945年8月15日) 直前の7月10日以降8月14日までに、在満邦人のうち18歳以上45歳以下の男性のほとんど全員約20万人、一説には5月以降で25万人を召集し国境付近にはりつけた。しかも彼等にはすでに小銃も帯剣も支給されず、ろくな被服とてない徒手の兵隊だった。
そして愚挙ともいえるこの員数合わせの「根こそぎ動員」により、満州(中国東北部)の日本人居留民社会、特に開拓団には高齢者・女性・子供だけが取り残される離散状態が現出し、まもなく深刻な二重悲 劇がおとずれる。
旧満州(中国東北部)とその地続きの大地に繰 り広げられた離散家族を襲う二重の悲劇。かたや国家権力によりにわかに戦線に送り込まれ、その果て捕らえられシベリアに移送されて死に至る男たち、かたや 一家の支柱を失い関東軍よりも見放され、たちまち戦乱の荒野に無残な彷徨を強いられる老幼婦女子の群れ。
これが傀儡国家「満州」をめぐる日ソ戦争であり、戦争のむごたらしい帰結であった。
ドイツにおける補償、日本における補償
(シベリア捕虜志 著 齋藤六郎 (全国抑留者補償協議会会長)による)
シベリア強制労働は本来、国際法上における「有 償」の行為であったが、政治的にはソ連の「賠償」とされたため、結果的には「無償」の過酷なものとなった。
この無償の労働は、もともと国の担うべき賠償の 責を国民の一部が肩代わりしたものとして、ドイツ連邦共和国においては逸早く、「戦争犠牲者の扶助に関する法律」「捕虜の親族の 扶養補助に関する法律」「帰還捕虜に対する援助に関する法律」等々、一連の補償措置が見られた。かくて、この法律は1952年に与野党一致の協力 とドイツ国民の強力な世論の下に成立を見たのである。
これらの法律の特徴は、国家補償の原則を踏まえてのものであったこと、即ち国家の側からの恩恵的なものではなく、捕虜の権利として定められたことである。
日本における補償
我が国においては捕虜のためとして特別になさ れた措置は皆無である。
例えば未復員者全員に対して取られたものとし て、留守中の月給を支払う形式が見られたが、これは月額わずか1,000円(昭和26年1月) であり、家族扶養手当は配偶者600円、家族400円の、雀の涙程度のものであった。捕虜直接に支給されたものは 舞鶴で支給された帰郷旅費の1,000円、後にも先にもこれだけである。
日独の措置を見て際 立っているのは、ドイツにおいては、復員兵を、国に代わって{賠償」を果たしてきた捕虜と、武装解除後、間を置かずに帰ってきた一般兵とに区別している事 である。実態に応じて区分していることは、この場合公平な措置を意味する。
「戦後の処理はすべて終了した。捕虜の補償は憲 法上認められない」
この間の処理にかかわった佐藤、田中、三木、福 田、大平、鈴木、歴代の自民党政府首相は、一貫してこのように主張している。戦争責任何処吹く風である。
捕虜を恥ずべきものとした東條時代のそれと、 何処に何の変わりがあろうか。国際法無視の最たるものである。
過る大戦で、同じ枢軸国家に属して闘い、敗北 したドイツと日本であったが、捕虜の処遇をめぐる政策において、雲泥の差が見られる。これは必ずしも法の解釈に相違があるからではない。傑出した政治家の 存在も又、無視できないものであろう。
ドイツの敗北は独裁者ヒットラーの死、ナチ党、 国防軍、政府の崩壊によってもたらされた。生き残った党、軍、政府の幹部は、戦犯としての追及を避けて潜伏、再び地上に現れることはなかった。戦後のアデ ナウアー内閣はドイツファシズムの批判者として出現した。
この内閣に、捕虜の権利を認めることについての 躊躇は無かった。
(註 コンラット・アデナウアーはドイツ・ケル ン市長であったが、1933年ヒットラーに罷免され、以後2回にわたる投獄の後、戦後になって解放された反ナチス自由主義者として知られる)
日本の敗戦は広島、長崎の原爆による都市の破壊 はあったが、領土で奪取されたのは沖縄一県のみ、内外合わせて5百万の軍隊、天皇統治機構も無傷のまま温存されることになった。
軍は復員後解体されたが主要部分は政府部門にと どまり、戦後処理に携わった。
階級、年功序列による「軍人恩給」の復活は、 これら旧勢力の発想によるものである。
ここでは、捕虜の名誉ある地位や強制労働に対す る補償は評価されなかった。
ドイツにおける補償と日本における補償の対比表
|
内 容 |
ド イ ツ で は |
日 本 で は |
|
|
1.捕虜の抑留中その扶養家族に対して
|
遺族扶助料と同額の扶養補助の実施 |
留守中の月給(月額)1000円(昭和26年1月) |
|
|
2.捕虜に対して |
一律300マルクの釈放手当の他、 帰国後、更に300マルクの衣料品、日常品手当を支給 |
帰郷旅費1000円(舞鶴で支給) |
|
|
3.捕虜の抑留期間は |
一切の社会労働保険に通算する |
||
|
4.捕虜の生活厚生のため |
帰国後の職業教育を受ける期間、次の手当てが支給される。 |
||
|
5.捕虜の抑留期間に応ずる手当の支給 |
①1945年以降3か月以上捕らわれた者に、捕虜として抑留期間1か月 につき30マルク |
「戦後強制抑留者問題特別措置法」 |
|
|
6.その他 |
家具、住居等のためにする貸付金制度を設けた他、就職紹介の優先権等の 措置も見られた |
昭和27年(1952年)当時1マルクは日本円換 算85円に相当)